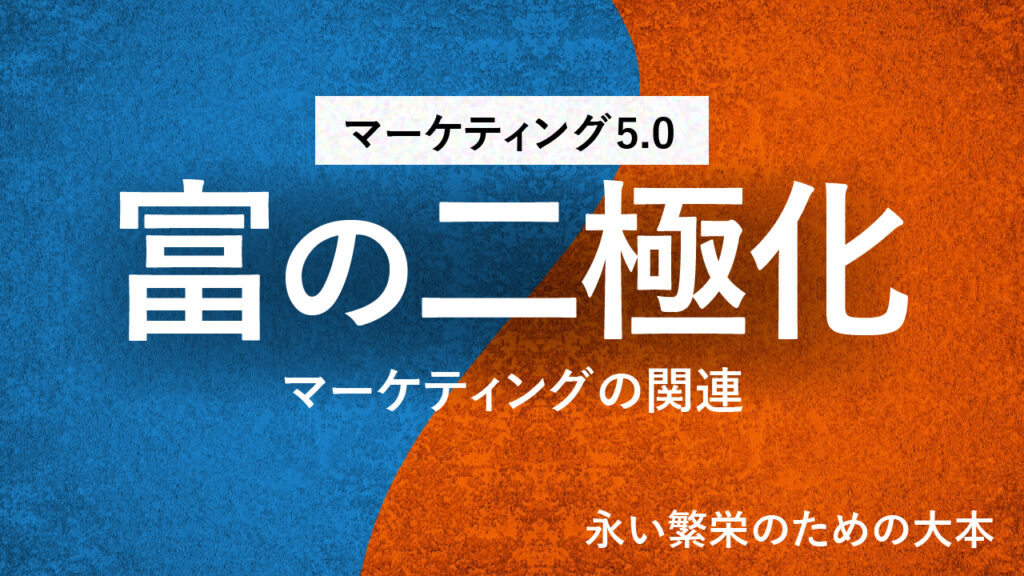ページコンテンツ
新規開業者のうち、1年以内の閉店が42~3%、3年以内の閉店が72~3%もあり、ラーメン店の平均寿命が2.4年という現在、全国のラーメン店の内、毎年1.6%の店が消滅しています。
従って、ラーメン店業界で起きている現実は、毎年生き残っていける店と、そうでない店が明確になり、さらに生き残っている店の中から、毎年1.6%が脱落しています。
しかし、毎年かなりの数の新規開店があるので、開店数と閉店数の差が1.6%(約300~400店)あり、業界全体でこれだけ減少していることが驚きです。
日本の人口はピークからまだ2~3%程度しか減少していないので、いかに店舗の減少率が激しいか、驚かされます。
言い換えれば、今後の日本においては、どんな分野においても、生き残ることが難しい時代に突入したことを我々は理解すべきです。
1.「散る桜 残る桜も 散る桜」という良寛和尚の教え通りです。
我々地球上でビジネスをしている者は、最終的に誰でも消え去る運命にありますが、その時期を少しでも後ろへ、未来へと努力を重ねています。
散り去る時期を少しでも未来へ延ばすためには、今回の小冊子の冒頭から何度も説明している通り、生産性を上げ、利益体質になることが一番の近道です。
生き残り、再投資するために必要なものは、再投資できる原資であり、再投資の対象は、人であり、ソフトであり、ハードです。
これは、どんなビジネスでも変わりません。
私は、毎月、各地でラーメン学校を開催し、世界中からの生徒さん達と常に話し合っていますが、このことはどの国であろうと、誰であろうと、変わることはありません。
2.売り上げを上げ、利益を出す戦略
さて、本冊子も後半に近づいてきました。
良い人を採用するために根本的に必要なことは、「儲かる店」「行列ができる店」を作ることです。
次に、売り上げを上げ、利益を出す戦略について4つのポイントをお伝えします。
高い価値(高い商品力)を提供する戦略
当社の東京支店の近くにラーメン二郎があり、いつも必ず、長い行列を作っています。なぜ、多くのお客さまが1時間以上の行列を作ってまで、人気店へ通うのでしょうか?
答えは簡単です。
どこにもないおいしさとか価値をその店に行けば、体験できるからです。あるいは、単においしいだけではなく、ボリュームも含めたその価値の高さです。俺のイタリアン、俺のフレンチが一世を風靡ふうびし、また、いきなりステーキが頑張っていましたが、これらの店舗の食材費比率は60%だそうです。
また、回転すし業界でトップに君臨しているスシローの原材料費率は50%で、外食産業全体の原材料費比率の平均値は40%になっています。
ところが、不振にあえいでいる、ほとんどのうどんそば店、ラーメン店は30%前後の原材料費比率で営業しています。これは、過去の習慣で、30~40年前のうどんそば店、ラーメン店ビジネスはその程度でも十分、お客さまを集めて繁盛できた名残があるためです。
従って、最も簡単に顧客満足度を上げ、売上を伸ばす方法は、原材料費率を上げることです。10%程度、原材料費率を高め、良い食材を使ったり、量目を増やすと、お客様の満足度も大きく変わります。
もし、店主に身銭を切って、自店の商品をその価格で喜んで食べるかと聞いたら、本音では、食べない方が多いと思います。ほとんどの店主は、原材料費比率を上げると、利益が出なくなると勘違いしています。
ところが実際に利益は、お客様の数によって決まります。
原材料費率を上げることは商品力を上げることにも繋がり、どんな店でも、どんなビジネスでも利益が出始めるのは、採算分岐点を超えてからです。そして、採算分岐点を大きく超えれば超えるほど、利益も大きくなります。ですから大きな利益を得るためには、多くのお客さまを獲得することが欠かせません。お客様の数が十分でないと、十分な利益をもたらすことはあり得ません。
それは当社の麺学校の経営講義で教えているビジネスモデルのシミュレーションすると簡単に分かります。
おいしさと見た目の綺麗さ
食べものを提供するビジネスである限り、おいしいのは当たり前であり、最近はグルメサイトの出現で、全国のライバル店と簡単に比較されるようになってしまいました。
私の経験から言えば、グルメサイトのスコアで3.5以上であれば、まず失敗して閉店することはあり得ません。
当社の麺学校の卒業生は、卒業して正しく手順を踏んで開店すれば、グルメサイトで、3.5以上のスコアを得ることは難しいことではありません。
そして、おいしさと同時に大切なことは、見た目の綺麗さで、最近はSNSの発達で、インスタ映えがもてはやされ、綺麗な盛り付けの料理はお客様がネット上で、拡散してくれます。
従って、今の時代は、自分で広告宣伝する必要が全くなくなりました。
ただし、開店時に準備不足でパニックになり、程度の低い料理を出してしまい、最初に3.0付近の点数が付いてしまうと、その後、挽回するのは大変です。
そのため開店時には絶対にチラシなどの広告宣伝をしてはいけないし、開店時には全てのスタッフが慣れていないので、多くのお客様を集める努力は絶対にしてはいけません。
この部分は、当社の麺学校では詳しく、厳しく教えています。
席数は売上と利益に大きなインパクトをもたらす
最近、当社の麺学校に来る生徒さんのほとんどが、10席から20席程度の小さい店舗を作ろうとします。
「なぜ、そんなに小さい店を作るのですか」と、確認すると、「従業員を雇いたくない」と回答する生徒さんが非常に増えました。
そして、「どんなお客様を呼びたいですか」と確認すると、「家族客を呼びたい」と、平気で回答するお客様が多いです。
人手不足時代が前提にあることは間違いないですが、まず、飲食店として成立して、お客様が行きたいと思える店ができるかどうかがもっと大切です。
まず、飲食店はお客様が来てくれないと成り立たりません。
今後の厳しい人手不足の時代を考えると、このような小さい店で、十分な利益を上げて優秀な人手を確保するのは至難の業ですが・・・。
優秀な人ほど、自分の将来を考えるはずですから。
5年先、10年先にここでいて、幸せになれる可能性があるかどうかは、入社する人にとっては、大変重大な問題です。
もし、同じ給料であれば、未来の可能性の高い職場に勤務したいはずです。
そのため、良い人材に選ばれる店になるためには、店舗の規模もそれなりに必要です。
店主と2人だけ、あるいは、2~3人だけの小さい店で、いつも店主と鼻を突き合わせているような店舗へ優秀な人は勤務したいはずがありません。
ラーメン業界で、グローバル化に成功した一風堂のような店舗を見れば、このことは非常に良く分かると思います。
私は、人手確保で成功し、チェーン展開している店のビジネスモデルを分析した結果、1店舗で月商1千万円程度の売上がないと、チェーン展開が難しいことに気が付きました。
ただ月商1千万円を売り上げるには、最低40席程度の店舗は必要です。
駐車場台数も大切な要素
日本で開店する場合、ほとんどの立地は駐車場の必要な自動車立地になっています。
それにもかかわらず、駐車場が少なかったり、もしくは無い状態で無理やり開店する人が後を絶ちません。
そのような悪い立地でも、絶対に失敗しない条件は、グルメサイトでのスコアが4.0以上の場合だけです。
スコアが4.0を超えると、どんな立地で開店しても必ず繁盛しています。
しかし、スコア4.0以上はうどんそば店、ラーメン店市場において、上位0.1%以内の非常に狭き門で、現実的には非常に難しいです。
また、郊外型店舗においては、どんなに席が空いていても、駐車場が不足していると、お客さまが店に入れません。
従って、郊外型店舗は席数以上に、駐車場台数も非常に大切な要素です。
当社では、お客様の利便性のために、常に商圏分析をし、必要な駐車場台数を割り出しています。(大和製作所の出店分析)

_上半身のみ_resize-300x283.png)