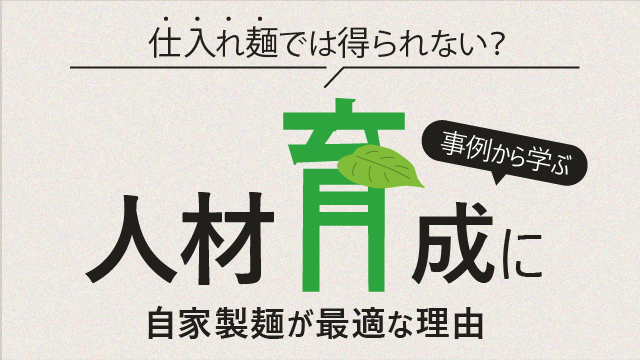ページコンテンツ
どの製麺機を選べばいいのでしょうか?
この質問に対する答えは、「場合による」です。では、何が「場合による」のでしょうか?次の3つの質問で答えることができます。
1. どのような麺を生産する予定ですか?
2. どの程度の量か?
3. どのような目的で生産するのか?
したがって、最適なタイプの製麺機を選択するには、現在および、将来のニーズと目標に最も適した製麺方法が重要です。
麺作りにあまり詳しくない人が「麺」を作ろうと思ったとき、多くの場合、一般的な麺(パスタと総称されることもある)を想像し、すべての製麺機が同じであると暗黙のうちに思い込んでいます。
似たような性質の多くの質問と同様、この質問に対する答えはもちろん「場合による」である。何が「場合による」のかは、次の3つの質問に答えることで明らかになります:
1. どのような麺を生産する予定ですか?
2. どの程度の量か?
3. どのような目的で生産するのか?
したがって、最適なタイプの製麺機を選択するには、現在および将来のニーズと目標に最も適した製麺ソリューションがどれであるかが重要である。
麺の製造にあまり詳しくない人が「麺」を作ろうと思ったとき、多くの場合、一般的な麺(「パスタ」と総称されることもある)を想像し、すべての麺製造装置が同じであると暗黙のうちに思い込んでいます。
I. では、まず麺の話題からですが、麺は以下のように分類できます。

1) 成分
2)製造方法
3) 生地の水和
4)加工・保存方法
1) 麺類とは、小麦粉や他の原料をペースト状にして、液体と混ぜて生地を作り、細かく切って作る食品のことを指します。
特殊な形をした珍しい麺を除くと、麺は主に以下のような材料から作られます。:
a) グルテン穀物(小麦)
b) グルテン以外のでんぷん質の穀物(米、そばなど)。
c) 穀物以外の植物のでんぷん質部分(こんにゃく、とうもろこしなど)。
d) 上記を異なる割合で組み合わせたもの
2) 麺を作る方法は以下のように分けられます。
a) 手延べ
b) 手延ばし
c) 機械による一方向の延ばし方
d) 多方向の機械練り
e) 機械で蒸す
f) 機械押出し
3) 麺類は水和の度合いによって、一般的に以下のように分類されます。
a) 低い
b) 中
c) 高水和
ここでいう水和とは、生地に直接加える液体の量だけでなく、原料そのものに含まれる水和(例:小麦粉やその他の成分中の水分)も含めた、生地に含まれる全体の水分量を意味します。
4) 麺類は、加工・保存方法によって、以下のように分けられます。
a)生(冷蔵)
b)生(冷凍)
c)乾燥(常温保存)
II. 量の概念は最終的には主観的なものですが、麺の生産量という点では、大きく3つのパターンに分けて語ることができます:
1) 非常に限られた量:10kg未満/1日50~100食未満の麺類
2) 大規模だが限定的な生産量:100~200kg未満 / 1日500~2000食未満の麺類
3) 非常に大きな生産量:1日200kg以上(このカテゴリーには、生産能力の高い工場規模の生産ラインも含まれます。)
III. 製麺の目的という点で区別できる:
1) 個人消費/限定的な業務用
2) 麺類専門小規模食品事業者向け供給
3) 大衆向け大量供給

麺の種類、生産量、生産目的など、それぞれのニーズや目的に応じて、特定のタイプの製麺機を使用して、最適な選択を行う必要があります。もちろん、状況や条件によっては、第三者から麺を調達する方が合理的である場合もあります。自社で麺を製造するという選択肢を否定する理由にもなり得ることも忘れてはなりません。
製麺機については、Ⅰ.2(製麺方法)、Ⅱ(生産量)が特に重要ですが、その他にもいくつかの項目を加えると全体像が見えてきます。
麺の種類、生産量、生産目的など、それぞれのニーズや目的に応じて、特定のタイプの製麺機を使用した技術的なソリューションを選択する必要があります。もちろん、状況や条件によっては、第三者から麺を調達する方が合理的である場合もあり、自社で麺を製造するという選択肢を否定する理由にもなり得ることを忘れてはなりません。
製麺機については、Ⅰ.2(製麺方法)、Ⅱ(生産量)が特に重要ですが、その他にもいくつかの項目を加えると全体像が見えてきます。
このように、製麺機は、以下のように分類することができます:
1. 生産方式
2. 製造量
3. 生地成分・水和
4. 機械の大きさ
5. 機械の価格
6. 機械の用途
ここでは、お客様のニーズや目標に最も適した製麺機を選ぶために、いくつかのシナリオを想定してみましょう。

1. 料理愛好家が家庭で個人的に食べるために、限られた量の麺を製造する場合、2つの可能な解決策があります:
a) 手で操作するローリングタイプの>パスタマシン<
または
b) 手動/電動押し出し式>製麺機<
この2つのタイプの機械は、中~多加水比の生地を処理することができ、グルテンやノングルテン穀物(圧延式と押し出し式の両方)、デンプン植物や米・そば粉(押し出し方式)から生地を作ることができます。
生産量は少なく、一般家庭や麺類を専門としない飲食業が、たまに提供するメニューの麺として使用する程度のニーズで十分です。機能性や生産量に制限があるため、数百万円以上の価格で販売されることはほとんどありません。
1. 料理愛好家が家庭で個人的に食べるために、限られた量の麺を製造する場合、2つの可能な解決策があります:
a) 手で操作するローリングタイプの>パスタマシン<
または
b) 手動/電動押し出し式>製麺機<
この2つのタイプの機械は、中~高水分比の生地を処理することができ、グルテンやノングルテン穀物(圧延式と押し出し式の両方)、デンプン植物や米・そば粉(押し出し式製造方法)から生地を作ることができます。生産量は少なく、一般家庭や麺類を専門としない飲食業が、たまに提供するメニューの麺として使用する程度のニーズで十分です。機能性や生産量に制限があるため、数百ドル以上の価格で販売されることはほとんどありません。
2.業務用製麺機には、上記のような選択肢のほかに、ニーズや原料、生産量に応じた、さまざまな製品があります。
小麦粉を使った一般的な麺を作りたい中小規模の食品事業者は、大きな卓上型のパスタ押出機やパスタシーター(生地を平らにする機械)、カッター(麺を切る機械)から始めることができます。
これらの機械を使えば、麺作りを主に行う事業所でも部分的に麺を提供する店でも、効率的に麺を作ることができます。
通常、内臓の生地ミキサーと組み合わせて、米粉や、そば粉から中~高水分のパスタや、その他の種類の類似麺、卵麺、グルテンフリー麺を作ることが可能です(押し出し式タイプ)
生産能力は、1時間当たり10kgの麺を作ることができ、価格は数十万円程度です。
2. 業務用製麺機には、上記のような選択肢の他に、ニーズや原料、生産量に応じた様々な製品がある。
小麦粉の生地をベースにした標準的な麺を作るには、麺の提供に全面的または部分的に依存している中小規模の食品事業者は、大容量の卓上パスタ押出機<またはパスタ>シーター/カッター<から始めることができます。
通常、内蔵の生地ミキサーと組み合わせて、米粉やそば粉から中~高水分のパスタやその他の種類の類似麺、卵麺、グルテンフリー麺を作ることができます(押し出しタイプ)。通常、1時間当たり10kgの麺を製造することができ、価格は数千ドル程度である。

機械の大きさと生産量は、この時点では、まだ「圧延タイプ」と「押し出しタイプ」の装置について、取り上げています。というのも、蒸す(フォー麺を作る)、手でこねる(うどん、そばを作る)といった製法の麺機は、その製麺工程の特殊性から、通常比較的大きな設置スペースと操作スペースを必要とします。
機械のサイズと生産量のこの時点では、まだ「機械圧延」タイプと「機械押出」タイプの装置について話しています。というのも、蒸す(フォー麺を作る)、手でこねる(うどんやそばを作る)といった製法の麺機は、その製造工程の特殊性から、通常、比較的大きな設置スペースと操作スペースを必要とするからである。

通常、製麺機の大きさは生産量に対応するために、製麺機が大きければ大きいほど、一定時間内に多くの麺を生産できます。そのため、より大きな生産量を達成するためには、通常第2項で述べたよりも大きなサイズの設備に投資する必要があります。
1時間に10kg以上の麺を作れる小型の製麺機は珍しいです。これは、特に麺を圧延したり手でこねたり蒸したりする設備の場合に当てはまります。しかし、たまにしか麺を使わないビジネスや、大規模な工場のような大量生産能力が不要なビジネスにとって、このような小型の製麺機は非常に重要です。特に、これらのビジネスが自分たちの製品に高い価格を設定するためには、家庭用機器や大量生産ラインで作られる麺よりも品質が高い必要があります。
大和製作所の製麺機は、家庭用製麺機よりも生産能力が高く、麺の品質が飛躍的に向上する一方で、大量生産用の大型工場ラインよりもはるかに小型で、麺の品質も向上します。
例えば、大和製作所の「リッチメン」シリーズでは、小麦粉、そば粉、米粉(またはそれらの組み合わせ)から1時間に100~250食の麺を作ることができ、最小1人の人数で済み、限られたスペースでも設置・操作できるコンパクトなサイズです。
小型の製麺機を使ってさまざまな種類の麺を作る場合、各レシピごとに特別な製麺手順が必要です。そのため、生産量を単純に質量単位で測定するのは難しいです。それぞれのレシピで、生地を混ぜる時間、伸ばす時間、薄くする時間、切る時間などが異なり、これが全体の生産量に影響を与えます。例えば、水分の少ない麺と比べて、水分の多い麺は平均してより多く(質量で)作ることができます。
この種類の製麺機の価格は、通常は約100万円から始まり、平均で約200万円ですが、生産量や機器の種類によっては300万円以上になることもあります。価格には輸送費も含まれるため、最終的な費用はこれより高くなることが多いです。
購入を検討する際には、ランニングコストや顧客サービス、安全基準や業界基準への適合性(国によっては法的要件もある)、レシピやアドバイスに関するメーカーからのサポートの有無など、多くの要素を考える必要があります。(弊社「麺機価格ガイド」参照)
製麺機を購入する際に最も重要なのは、今この記事をお読みのあなたが作りたい麺を製麺するのに十分な能力があるかどうかを確認することです。特に、標準的な運転モードで麺を作れるかどうかがとても重要です。
例えば、博多風ラーメンのような水分の少ない麺を作るには、生地をシート状にするために大きな圧力が必要です。これは一般的なパスタ用の製麺機の能力を超えることがあります。パスタ用の製麺機でこれらの麺を作ることが不可能ではないですが、このような目的で頻繁に使用すると、製麺機の耐久性が大幅に低下する可能性があります。
通常、製麺機の大きさは生産量に対応するため、つまり、製麺機が大きければ大きいほど、一定時間内に多くの麺を生産できるため、より大きな生産量を達成するためには、通常、第2項で述べたよりも大きなサイズの設備に投資する必要がある。
しかし、1時間当たり10kg以上の麺の生産能力を持ちながら、工場のラインよりも小さいサイズの製麺機は、特に圧延、手こね、蒸しなどの設備について言えば、稀である。しかし、時折麺を食べる程度で、大規模な工場ラインよりはるかに少ない生産能力を必要とする多くのビジネスが最も関心を寄せるのは、まさにこのカテゴリーの機器なのである。特に麺の品質という点では、これらのビジネスが製品に付ける値札を正当化するためには、消費者向け機器や大量生産ラインで製造される麺より優れていなければならない。
大和製作所の製麺機は、家庭用製麺機よりも生産能力が高く、麺の品質が飛躍的に向上する一方で、大量生産用の大型工場ラインよりもはるかに小型で、麺の品質も向上します。
例えば、大和製作所の「リッチメン」シリーズでは、小麦粉、そば粉、米粉(またはそれらの組み合わせ)から1時間に100~250食の麺を作ることができ、最小1人のオペレーターで済み、限られたスペースでも設置・操作できるコンパクトなサイズです。
小さいながらも重要な注意点は、製麺機で製造できる幅広い製品オプションがある製麺機では、各レシピに特定の製麺手順が必要となるため、生産量を質量単位で定義するのが通常かなり難しいことです。これらは、総生産量に大きな影響を与えます。例えば、生地を混ぜる時間、延ばす時間、薄くする時間、切る時間を考慮すると、低加水麺よりも高加水麺の方が平均して多く(質量で)作ることができる。
このカテゴリーの製麺機の価格は、通常1万ドル前後から始まり、平均2万ドル、生産量や機器の種類によっては3万ドル以上になることもあります(輸送費も最終価格を大きく上昇させます)。
もちろん、ランニングコスト、顧客サービス、各種安全基準や業界基準への適合性(国によっては法的に要求される場合もある)、レシピやアドバイスに関するメーカーのサポートの有無など、さまざまな要素を総合的に考慮する必要があります(弊社「麺機価格ガイド」参照)。
ここで重要なのは、購入しようとしている製麺機が、自分の求める麺を製造するのに十分な能力を持っているかどうか、そしてそれが例外的な場合だけでなく、標準的な運転モードとして可能であるかどうかを絶対に確認することである:
例えば、ある種の低加水麺(博多風ラーメンに使用されるような)は、生地をシート状にするために大きな圧力を必要とするが、一般的なパスタ用製麺機の能力を超えている(パスタ用製麺機がデフォルトでそのような麺を作れないというわけではないが、このような目的で常用しようとすると、耐用年数が大幅に短くなる)。

非常に大きな生産量(1日あたりの数百kgの麺を生産する中規模装置から、1日の生産量がトン単位で測定される大規模な工場規模ラインまで)は、通常、長い保存期間を持つ麺を生産するために用いられます。生産した麺を処理するための乾燥/放送装置と組み合わされます。このような生産の仕組みは、数千万円~数億円に達する多額の投資を必要とする場合があります。
このような工場では、さまざまなタイプの「パスタ」や「インスタントラーメン」を生産しています。
非常に大きな生産量(1日あたり数百キログラムの麺を生産する中規模装置から、1日の生産量がトン単位で測定される大規模な工場規模のラインまで)は、通常、長い保存期間を持つ麺を生産するために用いられ、生産した麺を処理するための乾燥/包装装置と組み合わされます。このような生産ソリューションは、数百万ドルどころか数十万ドルにも達する多額の投資を必要とする場合があります。
このような工場では、通常、さまざまなタイプの「パスタ」や「インスタントラーメン」を生産しています。

製麺機選びでは、さまざまな麺の種類と製麺機の特性を理解することが大切です。製麺機に「良い」「悪い」は一概には言えず、それぞれの機械の適性は、麺の原料や製造状況、お客様のニーズによって異なります。たとえば、家庭や少量生産向けの製麺機は大量生産には不向きであり、逆もまた真です。
中小規模の業務用製麺機をお探しの方には、以下のアドバイスがあります:
・適切な生産能力を持つ製麺機を選ぶことで、必要な量の麺を効率的に生産し、他の業務にも時間を割くことができます。
・将来的な事業拡大を見越して製麺機を選ぶことも重要です。多くの製麺機では段階的なスケールアップが難しいため、将来の需要増に対応できる余地を持たせることが理想的です。
・特定の麺の生産を計画している場合、その麺の生産に特化した機械を選択することが重要です。
例えば、低加水の硬い麺を生産する場合は、その目的に適した機械を選ぶことで、機械の寿命を延ばし、効率的な生産が可能になります。
今回は、製麺機選びのアドバイスとして、どのような麺があり、どのような製麺機があり、どのような製麺機を選べばよいのか、ざっとおさらいしてみました。
当たり前のことかもしれませんが、結局のところ、製麺機にどれが良い、悪いということはなく、それぞれの製麺機の良し悪しは、麺の原料や製造状況によって異なる場合があり、お客様のニーズや目的に合うかどうかによって決まります。量と用途(個人消費/商用利用)。
大和製作所は製麺機メーカーでありながら、家庭の麺愛好家やごく少量の麺を作りたい事業者には、比較的大型で生産量の多い製麺機は向かないかもしれないし、麺専門店のニーズに応えられる小型製麺機は、大量生産の業務用には生産能力が足りないかもしれない、ということをよく理解しています。
しかし、中小規模の業務用クラフト麺製造用の製麺機をお探しの方には、次のようなアドバイスができます:
– 自家製麺機を持つのであれば、必要な量の麺を短時間で生産できる生産能力を確保し、残りの時間を他の業務に集中できるようにすること(例えば、ラーメン店を経営するのであれば、麺を作ることだけにすべての時間を費やしたくないはずです)。
– 成長余地を確保することは理にかなっている:現時点ではそれほど多くの生産能力が必要でなくても、将来的に必要なくなるとは限らない(ほとんどの独立型製麺機では、段階的なスケールアップは不可能である)。
– 特定の 種類の麺の生産を計画している場合は、このタイプの麺の生産が標準的な動作モードではなくむしろ例外 である機械を選択しないでください。例えば、パスタマシンで低加水で硬い食感のラーメンを製造することは理論的には可能かもしれませんが、そのような目的で定期的に使用すると、マシンの寿命は間違いなく短くなります(おそらく、非常に早く)。
製麺機は実際に、使ってみて初めてわかることがたくさんあります。
製麺機は実際に、製麺してみて初めてわかることがたくさんあります。
もっと詳しく操作してみたいという方は、デモンストレーションでも操作可能です。
製麺機のスペック感や使用感、どんな麺が作れるのか、みなさまの疑問・質問にお答えしながら進めていきます。
もちろん製麺機のことだけでなく、麺や小麦粉のこと、分からないこと・気になることは何でもご質問ください!
全国のドリームスタジオで定期的に開催しています。

_上半身のみ_resize-300x283.png)